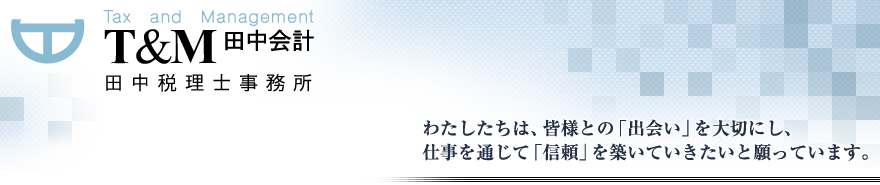ブログ
2017.12.22
平成30年4月1日施行 労災保険率の改定
昨日、厚生労働省より労災保険率の改定等について発表がありました。
こちらの改定は平成30年4月1日施行予定です。
今回の改定の3つのポイント
①平成30年4月から適用される新たな労災保険率を設定
それぞれの業種の労災保険率については下記リンクをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188912.pdf
②家事支援業務に従事する方について、労災保険の特別加入制度の対象に追加
家事支援従事者・・・家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者。
家事支援従事者は労働基準法上の「労働者」にはあたらず、労災保険の強制加入対象ではありません。
介護支援従事者に関しては以前から労災保険の特別加入が認められていましたが、改定により、家事支援従事者も特別加入が認められることとなりました。
③時間外労働の上限規制等の円滑な移行のため、中小企業事業主に対して、助成金の内容を拡充
「職場意識改善助成金」の名称が「時間外労働等改善助成金」となり、内容が拡充します。
また、3社以上の中小企業の事業主団体において、傘下企業の時間外労働の上限規制への対応に向けた取組に要した費用を助成する「団体推進」のコースが新設されます。
詳しい要件や内容等は下記のリンクをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188915.pdf
時間外労働等改善助成金については今年度の3倍以上の予算額を要求するようです。
時間外労働に関するニュースなどもあり、働き方改革は喫緊の課題となっているかと思います。
労働者の方が健やかに働くことができ経営も上手く回るよう、今まで通りではなく次の手を考える必要がありそうです。
・厚生労働省 報道発表 「労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html
2017.12.20
仮想通貨の所得計算方法
ビットコイン、イーサリアム、リップル等、仮想通貨の名前を日常でもよく耳にするようになりました。
仮想通貨は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。
そのため、仮想通貨に物理的に触れることはできません。
しかし仮想通貨を売却・使用することにより生じる利益については、原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
(※事業に付随して生じた所得と考えられる場合は事業所得となります。)
先日、国税庁は確定申告の対象となる仮想通貨の損益や具体的な計算方法等を公表しました。
以下はそちらについてまとめたものです。
仮想通貨の売却
仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合
例)
3/9 2,000,000円(支払手数料含む)で4BTCを購入。
5/20 0.2BTC(支払手数料含む)を110,000で売却。
110,000円 -(2,000,000円÷4BTC)× 0.2BTC = 10,000円
売却価額 - 1BTCあたりの取得価額 × 支払BTC = 所得金額
10,000円が所得金額となります。
仮想通貨での商品の購入
商品を購入する際に、仮想通貨で決済した場合
例)
3/9 2,000,000円で4BTCを購入。
9/28 155,000円の商品を0.3BTCで購入。
155,000円 -(2,000,000円÷4BTC)× 0.3BTC = 5,000円
商品価額 - 1BTCあたりの取得価額 × 支払BTC = 所得金額
5,000円が所得金額となります。
仮想通貨と仮想通貨の交換
保有する仮想通貨で他の仮想通貨を購入した場合
例)
3/9 2,000,000円で4BTCを購入。
11/2 他の仮想通貨(決済時点の時価600,000円)の決済に1BTCを使用。
600,000円 -(2,000,000円 ÷ 4BTC)× 1BTC = 100,000円
購入価額 - 1BTCあたりの取得価額 × 支払BTC = 所得金額
100,000円が所得金額となります。
仮想通貨の取得価額
上記のように単純な例であれば計算は簡単です。
しかし、ビットコインの取引をしていらっしゃる方は1年の内に、買ったり、売ったり、商品を買ったり、他の仮想通貨と交換したり・・・様々な取引をされるのではないでしょうか。
そのような場合、仮想通貨の取得価額は下記のように移動平均法を用いて算定します。
(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)
例)
3/9 2,000,000円で4BTCを購入。
5/20 0.2BTCを110,000円で売却。
9/28 155,000円の商品を0.3BTCで購入。
11/2 他の仮想通貨(決済時点の時価600,000円)の決済に1BTCを使用。
11/30 1,600,000円で2BTCを購入。
①移動平均法の場合
3/9に取得した1BTCあたりの取得価額 2,000,000円÷4BTC=500,000円/BTC
11/30の購入直前において保有しているビットコインの簿価 500,000円×(4BTC-1.5BTC)=1,250,000円
11/30の購入直後における1BTCあたりの取得価額 (1,250,000円+1,600,000円)÷(2.5BTC+2BTC)=633,334円(1円未満切り上げ)
②総平均法の場合
(2,000,000円+1,600,000円)÷(4BTC+2BTC)=600,000円/BTC
確定申告のために、とにかく記録!記録!記録!という感じですね・・・
複数のウォレットでビットコインを管理していたり、複数の取引所で取引していたりされる方は特に手間がかかりそうです。
取引履歴から税額を計算してくれるサービスも開発されているようですが、開発中のものであったり、いくつかの取引所に対応しているものであったり、
すべてを網羅するものは、まだ無いようです。
確定申告に備えて、情報収集しておく必要がありそうです。
・国税庁 タックスアンサー ビットコインの課税関係
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
・国税庁 仮想通貨に関する所得の計算方法等について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
2017.12.15
社員の給与を上げて法人税を減らす?
法人税の所得拡大促進税制をご存知でしょうか。
ざっくりおおまかにお伝えすると「社員の給与を上げたら法人税額を安くしますよ」という制度です。
制度自体は以前からあるのですが、昨日、平成30年度税制改正大綱で改組が発表されました。
大企業と中小企業では制度が違うため、今回は中小企業の所得拡大促進税制についてご説明させていただきます。
所得拡大促進税制とは・・・
<対象者>
青色申告書を提出する中小企業者等
<対象事業年度>
2018年(平成30年)4月1日~2021年(平成33年)3月31日までの間に開始する各事業年度
<要件>
国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が1.5%以上である
<効果>
給与等支給増加額の15%の税額控除ができる
※ただし、控除税額は、当期の法人税額(所得税額)の20%を上限とする
計算例!
頭の良い方はすぐに理解されるのかもしれませんが、一読しても「?」が浮かびます。
要件のところは特に何をおっしゃっているのやら・・・
つまり、例を示して計算していくと・・・
ホニャララ商店の場合
・2019年(平成31年)1月1日から新事業年度。
・従業員 Aさん
ずっと昔から働いています。
2018年は月30万円受け取っていて、年額は360万円。
2019年は月1万円上がって、年額372万円です。
・従業員 Bさん
Aさんと同じくずっと働いています。
2018年は月20万円受け取っていて、年額は240万円。
2019年は月1万円上がって、年額252万円です。
・従業員 Cさん
2018年10月に働き始めました。
2018年の給与は30万円。
2019年の給与は120万円。
まず従業員をふるいにかけ、継続雇用者だけを計算に含めます。
継続雇用者とは当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある国内雇用者で一定の者。
ホニャララ商店の場合は、Cさんは途中で働き始めたため計算には含めません。
平均給与支給額は今年度の ( 372万円 + 252万円 ) ÷ 2人 = 312万円
比較平均給与等支給額は前年度の ( 360万円 + 240万円 ) ÷ 2人 = 300万円
312万円 - 300万円 = 12万円
12万円 ÷ 300万円 = 0.04(4%)
「1.5%以上なので、ホニャララ商店は税額控除を受けられる!」ということになります。
15%の税額控除が25%に!?
さらに要件が厳しくなりますが、
①上記の割合が2.5%以上である
②教育訓練費の額が前年と比較して10%以上増加している
もしくは
経営力向上計画の認定を受け、計画に従って経営力向上が行われた証明をされた
この2つの要件をどちらも満たすと、給与等支給増加額の25%の税額控除ができます。
※ただし、控除税額は、当期の法人税額(所得税額)の20%を上限とする。
気を付けないといけないポイント
①設立事業年度は対象外!
以前の制度では、設立事業年度でも税額控除を受けられましたが、設立事業年度は対象外となってしまいました。
②今年度と前年度のまるまる2年、毎月給与をもらっている人が必要!
「継続雇用者」の範囲が見直され、まるまる2年毎月給与をもらっている人がいない場合は、要件を満たさず、適用されないこととなりました。
他にも、平成30年度税制改正大綱で多くの税制見直しや、新しい税制の創設が発表されています。
税金は時代を映す鏡のようなものだと思いますので、ご覧になってみてください。
ご相談もお待ちしております。
・平成30年度税制改正大綱
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/136400_1.pdf