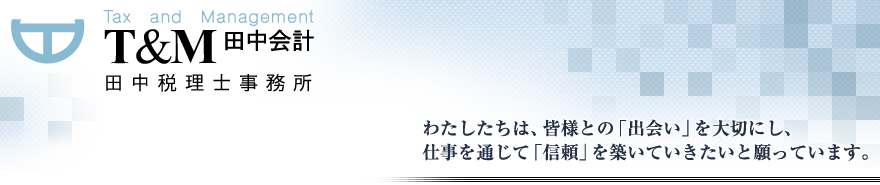ブログ
2017.12.01
相続税対策 111万円の贈与
平成27年1月1日の相続税制の大改正により、相続税の申告割合が従来の2倍に増加しています。
基礎控除額の引き下げが行われたために、改正前の制度においては相続税を払う必要がなかった方が、改正後においては相続税を払う必要がある方になってしまったというのが大きな原因でしょう。
改正前は被相続人(亡くなられた方)100人中4人の相続について、相続税が課税されているような状況が続いていました。
しかし、改正後は被相続人100人中8人の相続について、相続税が課税されています。
他人事と思っていたら税務調査が来て、相続税を払うことに・・・ということも起こりうる状況です。
相続税の節税のための最大のポイントは「生前にやるべきことをやっておく!」ということです。
亡くなられた後にできることというのは、
・土地の評価額をできるだけ小さくする
・特例にあてはまるものがあるかチェックする
・正しく申告し、加算税がかからないようにする
など・・・生前にできることに比べてかなり少なく、効果もそれほど大きくはありません。
少しでも不安に思われる方は、生きているうちに、それもできるだけ早くに始めておくのが最善の方法です。
そこでここからは、「年間の贈与税の非課税枠110万円を少し超えた111万円を贈与し、わざと少額の贈与税を支払うことで、贈与の証拠を確実に残す」という方法についてご説明します。
相続税のことで不安をお持ちの方でしたらご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、実はこれがなかなかのクセモノなんです。
ポイントを理解していないと、「これは結局のところ、贈与したものではなく相続財産ではないか」と疑われ、対策の努力虚しく、相続税を支払うことになるかもしれません。
<<贈与税の非課税枠110万円>>
贈与は年間110万円までなら課税されません。
しかも、110万円の基礎控除額は贈与を受ける人一人当たりの金額であるため、
子・孫合わせて5人に10年間贈与するとすると・・・
110万円×子・孫5人×10年=5,500万円
5,500万円の財産を贈与税・相続税を払わずに子や孫に移転することができます。
取り組むのが早ければ早いほど、その節税効果は高まります。
<<じゃあどうして110万円じゃなくて111万円?>>
これは、110万円の贈与を否定され、相続税を課税されることを防ぐためです。
例えば、毎年非課税の110万円ずつ10年間お子さんに贈与していこうと考え、お子さん名義の通帳を作成、そこへ毎年110万円ずつ入金。
その後お父さんが亡くなって相続が開始したときに、
「そういえば父親が生前贈与をしてくれている私名義の通帳があると言ってたな、これは贈与してもらったし、相続財産には含まれないな」と考え、相続財産として申告していないとします。
これでOKと思っていた矢先に言われることは「この通帳はお子さんの名義になっていますが、実質はお父さんの財産ですね。相続財産に含まれるので相続税が課税されますよ」です。
贈与を否定されると、せっかくの努力も水の泡になってしまいます。
そこで、111万円を贈与し、わざと少額の贈与税を申告して支払うことで贈与の証拠を残します。
贈与の証拠を残すことで、「これは贈与じゃなくて相続だ!」と言われるのを防ごうという目的です。
<<111万円贈与で気を付けなければならないポイントって?>>
なるほど、111万円ずつ贈与すればいいのか!と思ったところで注意点です。
111万円贈与はなかなかのクセモノですので、注意点がいくつかあります。上記の例も交えてご説明します。
①贈与税の申告は贈与を受ける側が記入して申告すること!
贈与が成立するカギは「あげた・もらったの契約があったか」です。
もしお父さんが111万を入金して、贈与税の申告書も作成して提出していると「もらったという意識があるか?きちんと贈与の契約ができているのか?」ということが疑われ、贈与が否定されることになりかねません。
②契約書を交わしておくと尚良し!
残せる証拠はすべて残しておく方が安心です。お正月やお盆休みなどいつでもいいので、1年に1度集まり、毎年契約書を作成しましょう。契約書にはきちんと自署し、契約書に押した印鑑は自分のものをそれぞれ保管することが大切です。
③通帳・銀行印は贈与を受けた側が保管し、自由に使える状態にしておく!
お父さんがお子さん名義の通帳・銀行印を保管してお子さんが自由に使えない状態だと、「実質的にはあげたことになってないんじゃない?」ということで、贈与が否定される可能性があります。
あれやこれやとややこしいのですが、残される方・次世代の方の今後を考えるととても大切なことだと思います。
こういったややこしい問題のある部分はご自身で調べることも一つの方法ですが、専門家である我々にご相談いただく事がのちのちの安心につながると思います。
疑問・不安があればお気軽にご相談ください。
・国税庁 平成27年改正
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/02.pdf
・国税庁 平成27年分の相続税の申告状況
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/sozoku_shinkoku/index.htm
・国税庁タックスアンサー 贈与税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
2017.11.29
皆様のお手元にも届くかも?『マイナンバー等確認リスト』
先日、11月13日より政府が運用するオンラインサービス『マイナポータル』が本格運用を始めました。
マイナンバーカードを使ってマイナポータルへログインすることで、自分にぴったりの情報を得られたり、行政手続きの申請もマイナポータル上で行うことができる等、今後もサービスを拡充させていく予定のようです。
また、今まで試行運用だった協会けんぽとの情報連携も同じく11月13日より本格運用が始まっています。
高額療養費等の申請に際して、マイナンバーを通じて税情報の照会を行うことができるため、(非)課税証明書等の添付が不要となります。
こういった中で、日本年金機構も届出の省略や添付書類の省略などを目指し、マイナンバーの収録・確認作業を進めているようです。
しかし日本年金機構が管理している氏名等の情報と、住民票に記載される情報に相違がある等の理由により、マイナンバーの確認ができない被保険者がいるとのこと。
もし、同一事業所内に「マイナンバーが確認できている人」と「確認できていない人」が両方いらっしゃると・・・
例えば被保険者がお引越しをしたとすると、
●マイナンバー確認OKの方→住所変更届の届出不要
●マイナンバー確認NGの方→住所変更届の届出必要
事業主様が「この被保険者はマイナンバーの確認が取れている人かどうか」を把握し、届出が必要かどうかを判断し、必要な方については届出をしてもらわないといけないという、大変面倒な事態が起こってしまいます。
マイナンバーの便利さを享受しようと思うと、全員のマイナンバーの確認が取れていることが重要です。
日本年金機構はこの「確認できていない人」の確認作業を進める予定で、
「確認できていない人」が在籍する適用事業所の事業主様あてに、12月中旬以降、順次『マイナンバー等確認リスト』を送付し、事業主様にマイナンバーの確認への協力をお願いしていくようです。
お手元に届いた事業所様は、生みの苦しみに耐えて協力していただくと今後の便利につながるかと思います。
『マイナンバー等確認リスト』に関するお問い合わせは、平成 29 年 12 月 20 日以降に照会ダイヤルを設置するそうで、改めてリスト送付先事業主様にお知らせがあるようです。
・厚生労働省 マイナポータルとは
http://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/
・協会けんぽ マイナンバー制度による情報連携の詳細
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/sb5010/291110001
・日本年金機構 マイナンバー等確認リスト
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf
2017.11.27
就職内定率の上昇と内定辞退
先日厚生労働省より発表された資料によると、
平成30年3月卒の大学生の就職内定率(10/1時点)は75.2%だそうで、
これは調査を始めた1996年以降で過去最高の数値とのこと。
就職内定率はここ7年ほど(ほとんど)右肩上がりで上昇しているのですが、
この売り手市場にともなって問題となっているのが「内定辞退」と「内定者の囲い込み」です。
内定辞退の理由としてよく聞かれるのは、
「勤務条件が合わない」「他に内定をもらった」「社風が合わない」などなど。
複数の企業から内定をもらう学生さんが多く、企業間の競争も自ずと激しくなっているようです。
このような状況で競争を勝ち抜くべく、内定後のフォローをきめ細かく行う企業が増えているようで・・・
・企業から内定者への定期的な連絡
・入社前教育
・先輩社員との交流会
・内定者同士の交流会
・SNSでのフォロー
こういったフォローを行っているそうです。
しかし、こういったフォローも度が過ぎると「内定者の囲い込み」となり企業のマイナスイメージになりかねません。
SNSで誰もが情報を発信できる時代ですので、内定者1人に与えたマイナスイメージが、社会全体からのマイナスイメージに簡単に変わってしまいます。
「株式会社〇〇にこんなことを言われた!ブラック企業だ!」なんてつぶやかれることになりかねません。
少し前までは企業は「選ぶ」側だったかもしれませんが、どんどん「選ばれる」側にシフトしています。
これまでは、内定者が「選ばれるために企業に何をどう伝えるか」試行錯誤してきましたが、
今度は、企業が「選ばれるために内定者に何をどう伝えるか」試行錯誤することになりそうです。